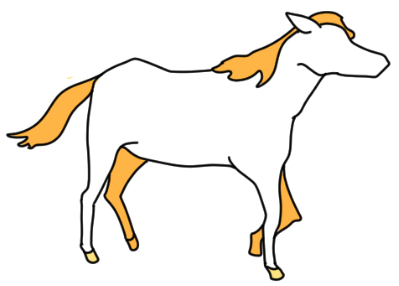2025年8月20日、「麻布大学出る杭プログラム総括シンポジウム:好きを力に とがった才能を引き出す教育プログラム」を開催しました。
このシンポジウムでは、文部科学省の「知識集約型社会を支える人材育成事業 メニューⅡ」において、全国で唯一採択された本学の「麻布出る杭プログラム」の5年間の成果を振り返るとともに、今後の展望を広く共有しました。(※2022年度の中間評価では、最高ランクである「S」を獲得)
Index

基調講演では、村上雅人先生から、「夢をつなぐ大学教育」をテーマに御講演をいただき、夢をつなぐ大学とは、教員・職員・学生に夢と希望を与え、勇気づける存在であり、本来人が持つ能力と可能性を最大限に引き出す「エンパワメント」の実践を目指す大学であるという視点に基づき、本プログラムが「夢をつなぐ大学教育の規範となる」と高い評価をいただきました。

次に、菊水健史副学長から、本プログラムの誕生のきっかけや出る杭プログラムのイメージイラストのストーリーを元に、5年間で実現した成果や、大学教育における課題と展望について報告が行われました。この報告は、実体験に基づく一貫した姿勢や力強い思いが伝わるものであり、参加者の心をつかみ大きな理解を促しました。
特に、教学IRによるプログラムの効果測定や、教職協働・信頼・共感による相互作用が、本プログラムの成果を後押ししていることも示されました。

続いて、前田高志センター長から、高大接続の成果と取組内容について報告がありました。この5年間で飛躍的に進んだ大きな要因として、教職協働で一体となって進めたことや、高校教育に造詣が深い方を客員教授として招聘するなどを挙げ、高校・大学を取り巻く最新の動向に合わせた、柔軟な体制で取り組んでいることが強調されました。



この後、実際にプログラムに参加した学生3人から、参加した理由、取り組んだ研究、大変だったこと、嬉しかったこと、身に付いた能力、これらのプログラムに興味のある高校生や本学学生に向けたメッセージがありました。



パネルディスカッションでは、菊水健史副学長がファシリテーターとなり、大学教員・高校教員・学生のそれぞれの立場から、質疑応答も含めて成果や今後の展望について議論が行われました。

本シンポジウムの閉会にあたり、村上賢学長から、「好きを力に」という理念のもと、学生一人ひとりの個性を伸ばし、社会で活躍できる人材の育成を今後も推進する旨の挨拶があり、本学の今後の教育へ希望が示唆されました。

\関連情報/

2025年12月24日
立派な出る杭になろう!麻布出る杭研究プロジェクト7期生交流会の様子

2025年12月23日
相模女子大学高等部ライフサイエンスコースの生徒さんが高大連携講座で麻布大学に来校

2025年11月20日
県立相模原高等学校の生徒さん高大連携講座で麻布大学に来校

2025年11月11日
北豊島高校にて「夢探し工房」の出張授業に加瀨先生が登壇

2025年9月11日
明星高等学校の生徒さんが高大接続プログラムの一環として麻布大学に来学しました

2025年9月9日
【高大連携校・接続校限定】夏期体験実習及び夏休み研究室体験を実施いたしました