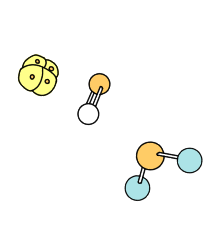小林直樹(食品安全/分子生物学)、島津德人(病理学)
Avian Gastric Yeast (AGY) 症は、世界中のオウム・インコ類やフィンチ類などのペットの鳥で蔓延している感染症です。原因はMacrorhabdus ornithogasterという真菌の感染で、代表的な症状は、食欲不振、嘔吐、下痢などです。死んでしまう鳥がいる一方で、無症状の不顕性感染も知られています。
ペットの鳥の他にも、飼育下のダチョウ・ニワトリ・カラス・ハト・オオハシなどからの報告や、野生の個体からの報告も少数あることから、今後、流行が起こる可能性があります。
原因菌のM. ornithogasterは、細⾧くてとても特徴的な形をした酵母です。2004年に特定されましたが、保存が難しいため、世界中のどこにも菌株のストックがありません。研究報告が少ないため、どの鳥種が菌を保有するのか、自然界のどこに分布するのか、どんな性質を持つのかなど、ほとんど分かっていません。
また、検出効率の高い検査法の開発も進んでおらず、臨床の場では多くの場合剖検による組織切片や糞便の鏡検によって診断されています。症状のある病鳥からの検出率は、鏡検では50%以下、PCR診断でも60%以下と低く、迅速な新規診断法の開発が望まれます。
これまでに、動物病院のインコ類・文鳥の糞から菌株の分離培養に成功しており、DNAの解析を進めています。また各地の動物園や野鳥保護施設と連携し、様々な鳥種からM. ornithogasterの検出を試みています。野生や飼育下の鳥類の生態や保護に興味がある学生や、微生物感染症のメカニズム、先端的なDNA実験手法に興味がある学生の研究参加をお待ちしています。