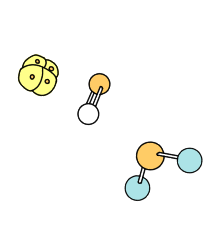新田梢(植物生態学)、片平浩孝(環境生物学)、髙田久美子(気候システム学)
地域の緑地は、希少な動植物の逃避地となり、自然を身近に感じられる憩いの場所として人々に利用されてきました。一方、その重要性が満足に把握されないまま開発が進んだり、適切な管理がされずに放置されたりして、出現種数の減少や外来種侵入など、さまざまな問題がおこっています。このプロジェクトでは、地域の緑地の植物を調べ、評価します。身近な植物調査をきっかけとして、他の生物との関わりはもちろん、地形や気候変動との関係など、総合的な視野から緑地を検討します。
学生のみなさんは、野外でのフィールドワークを通して、基礎的な調査技術、植物を中心とした野生生物・自然環境の基礎知識などを習得していきます。野外での調査に興味がある皆さんの参加をお待ちしています。